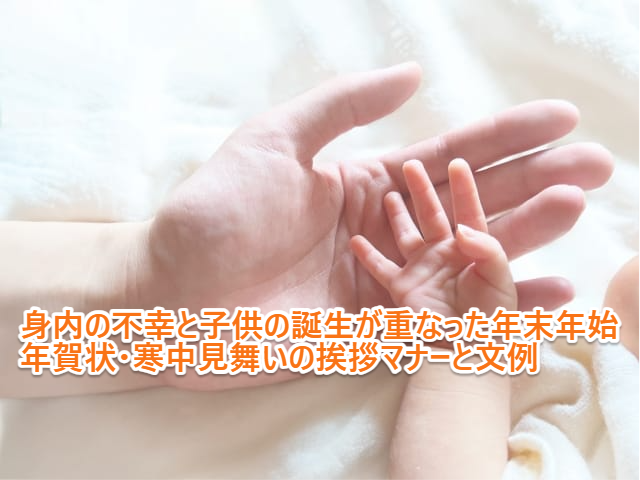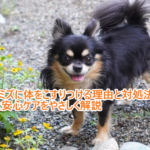年末年始という特別な時期に、喜びと悲しみが同時に訪れることもあります。
「身内の不幸があり喪中だけれど、同じ年に子供が生まれた」──
そんな時、年賀状や挨拶の仕方に迷う方は多いです。
お祝いごとを控えつつも、大切な方へ新しい命の誕生を伝えたい。
その気持ちはとても自然なものです。
この記事では、マナーの観点から「出産報告」と「喪中の挨拶」を両立させる方法を、寒中見舞いや文面例を交えてやさしく解説します。

喪中と出産報告が重なったときの基本マナー|「年賀状は控える」が原則

写真はイメージです。
身内の不幸があった年は、一般的に「喪中」として翌年の年賀状を控えます。
これは、年賀状が「新年を祝い合う」性格を持つためです。
一方で、出産というおめでたい出来事があった場合でも、喪中期間中はお祝いを控えるのがマナーとされています。
そのため、「出産報告を年賀状で伝える」のは避けた方が良いとされています。
では、まったく報告しないのが正しいのでしょうか?
実はそうではありません。
年賀状の代わりに「寒中見舞い」で出産を伝える方法があります。
寒中見舞いは、松の内(1月7日頃)を過ぎてから立春(2月4日頃)までに出す季節の便り。
お祝いではなく「季節の挨拶」として出せるため、喪中の時期でも失礼になりません。
寒中見舞いの中で、「昨年は身内の不幸がありましたが、同じ年に子どもが生まれました」と丁寧に添える形がもっとも自然です。
マナーの要点としては以下の3つです。
👉️ 年賀状は控える
👉️ 寒中見舞いで近況とお礼を伝える
👉️ 出産報告は控えめに添える
喜びを前面に出すのではなく、「静かに報告する」気持ちで文面を考えるのがポイントです。
寒中見舞いで出産を伝える文面のコツ|「控えめに」「心を込めて」

写真はイメージです。
寒中見舞いで出産を報告する場合、トーンは控えめながらも温かく伝えることが大切です。
「喪中なのでお祝い事は控えていますが、新しい命を授かりました」というように、淡々とした中にも感謝を込めるのが理想的です。
文例を挙げてみましょう。
――――――――――――
寒中お見舞い申し上げます。
昨年は○○の死去に際し、あたたかいお心遣いをいただきありがとうございました。
おかげさまで悲しみの中にも、同年〇月に第一子(長女/長男)が誕生し、新たな希望を感じております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
――――――――――――
このように「喪中」と「出産報告」の両方を一文ずつ触れることで、礼を失せずに両方の思いを伝えることができます。
出産写真を添えるのは控える方が無難ですが、親しい友人には別途私信で写真を送るのも良いでしょう。
また、宛先によって文面のトーンを調整するのもポイント。
たとえば、職場の上司には丁寧に、親しい友人には少し柔らかく書くことで、あなたらしい誠実さが伝わります。
出産報告を伝えるタイミングと方法|春以降に「お知らせはがき」もおすすめ

寒中見舞いで報告できなかった場合や、もう少し明るい形で伝えたい場合は、季節が落ち着いた春以降に「出産のお知らせ」として改めてはがきを出す方法もあります。
この場合、喪中明け(一般的に忌明けの翌日以降)に、「時期を改めてお知らせいたします」という形で伝えれば問題ありません。
文面例:
――――――――――――
ご挨拶が遅くなりましたが、昨年○月に〇〇(子どもの名前)が誕生いたしました。
悲しみの中にも新たな命に励まされ、家族一同日々を大切に過ごしております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
――――――――――――
このように「命のつながり」「家族の支え」などの言葉を添えると、読んだ人の心にも優しく響きます。
出産報告=派手なデザインというイメージがありますが、白やグレー、淡いピンクなど落ち着いたトーンのデザインを選ぶと品の良い印象になります。
また、最近ではオンラインはがきサービス(しまうまプリント・挨拶状ドットコムなど)でも喪中と出産を両立したテンプレートが登場しています。
こうした最新サービスを活用することで、マナーを守りつつ気持ちを丁寧に届けることができるでしょう。
まとめ
身内の不幸と子供の誕生が重なった年は、気持ちの整理もつかない中でのご挨拶に悩みますよね。
基本は「年賀状は控え」「寒中見舞いで近況を伝える」。
そして、春以降に改めて穏やかに出産報告をするのが最も自然で失礼のない形です。
悲しみの中にも、新しい命への感謝や希望をそっと添える──
それが大人の女性としての上品なご挨拶です。
形式だけにとらわれず、「相手への思いやり」を第一に、あなたらしい言葉で伝えてみてくださいね。