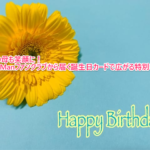※本記事は筆者が調べた内容をもとにまとめた一般的な情報であり、医療の専門的な判断や診断を行うものではありません。
体の不調や不安がある場合は、必ず医師など専門家にご相談ください。※
暑い季節、外を歩くのはためらわれますね。
特にアラフィフ、50代の主婦にとっては体力維持・ダイエットとして、自宅でかさばらずにできる“踏み台昇降”はとても魅力的です。
私自身も、「膝からジャリジャリ音がするけれど、痛みはないし違和感もない…でも音が気になる」という体験をしました。
実は、この“ジャリジャリ音”、専門的には「クレピタス(関節雑音)」と呼ばれるもので、必ずしも異常とは限らないのです。
本記事では、最新の医学情報や専門家の意見をもとに、この音の正体や、安全に踏み台昇降を楽しむためのポイントを、わかりやすくお伝えします。
あなたの「踏み台昇降への不安」が軽くなるようにまとめましたので、ぜひご一読ください。
膝から聞こえるジャリジャリ音って何?原因は?

写真はイメージです。
膝の関節で聞こえる「ジャリジャリ音」は、医学用語で「クレピタス」と呼ばれることがあります。
これは、関節内部の気泡がはじける音、軟骨の摩耗、あるいは滑膜内に存在する浮遊体(軟骨のかけらなど)が動くことで生じる音が原因とされています。
特に痛みや腫れがなければ、多くの場合「生理的音」とされ、日常的に見られる無害な現象です。
一次情報として、整形外科の専門医による解説や教科書にも「関節雑音があっても痛みがなければ、まずは経過観察でよい」と記載されています。
ただし、稀に軟骨のすり減りや関節炎など、将来的なトラブルの前触れである場合もあるため、音が継続的かつ強く、特に痛みや腫れが出てきたら専門医への相談を推奨します。
さらに、日本整形外科学会の情報によると、膝関節は体重を支える大きな関節であるため、40代以降では軽度の軟骨変性や半月板のすり減りによって雑音が出やすいとされています。
つまり「年齢に伴う自然な変化」であるケースも多いのです。
また、膝の音には種類があり、
「パキッ」「コキッ」といった瞬間的な音は、靭帯や腱が骨の突起に引っかかってはじけることで鳴る場合があります。
「ジャリジャリ」「ゴリゴリ」と持続的に聞こえる音は、軟骨表面の摩耗や関節液の性質変化と関わることが多いです。
「プチプチ」とした軽い音は、関節液の中の気泡が弾けることで起こる生理的な現象で、特に問題ないとされています。
「音はするけれど、痛くないし日常動作に支障がない」というケースは、加齢とともに軟骨や滑液の変化に起因することが多く、「経年的に見られる現象」として扱われます。
もちろん、ご心配な場合は整形外科でレントゲンやエコーなどを用いた診察を受けるのが安心です。
また、膝周りの筋肉(大腿四頭筋やハムストリングス)を意識的に鍛えることで関節を支える力が増し、結果的に雑音が減少することもあります。
リハビリの現場では軽いスクワットやレッグエクステンションなど、膝にやさしい筋トレが推奨されることがあります。
踏み台昇降は「ジャリジャリ音がしても大丈夫?」安全に続けるポイント

写真はイメージです。
結論から言うと、膝に痛みや腫れのない状態で、かつ整形外科医から運動制限がない限り、踏み台昇降は続けても問題ないことが多いです。
もちろん、誰にでも全く同じように安全とは言い切れないので、自分の膝の状態を毎回確認しながら取り組むことが大切です。
一方で安心して続けるために、以下のポイントを守りましょう。
準備運動・ストレッチをしっかり
踏み台昇降前には、太もも前(大腿四頭筋)やふくらはぎ、膝裏を軽くほぐすストレッチをおこなうことで、関節への負担を減らせます。
さらに、股関節や足首も合わせてほぐしておくと、膝への集中した負担を分散でき、より安全です。
踏み台の高さに注意
床から10~15 cm程度の高さが理想的。
高すぎると膝に負担がかかりやすく、音や違和感が強くなる可能性があります。
慣れてきたら20 cm程度まで調整してもよいですが、必ず無理のない範囲で行いましょう。
負荷を徐々に上げる
初めはゆっくり10分程度からスタートし、慣れてから少しずつ時間や頻度を増やすと安心です。
週に3回から始め、体調が良ければ5回へと増やしていくなど、段階を踏むと継続しやすくなります。
時間を伸ばすだけでなく、テンポを上げたり手を振る動きを加えたりと、工夫することで全身運動に近づけることも可能です。
クッション性のある靴やマットの活用
滑りにくくクッション性のある靴、あるいは踏み台の下に薄いマットを敷くことで衝撃が軽減され、関節雑音や不快感の軽減につながります。
裸足で行う方もいますが、膝や腰に不安がある場合は靴を履いたほうが安定感が高まります。
違和感・痛みの兆候に注意
音はあっても、例えば膝上や膝の内側に痛み、腫れ、熱感が現れたらすぐに中止し、専門医の診察を受けましょう。
また、体が重だるいと感じる時や睡眠不足の時は、あえて休養日を設けることも大切です。
日常生活でのサポートも意識する
階段を上る際に手すりを活用したり、長時間の正座を避けたりと、膝にやさしい生活習慣を心がけることも踏み台昇降を長く続ける秘訣です。
食事面では、たんぱく質やカルシウム、ビタミンDなど骨と筋肉を支える栄養を意識すると効果的です。
踏み台昇降を始める際には、事前にストレッチを行い、10cmほどの踏み台を使って、1日10分程度から始める方法がよく紹介されています。
数週間続けることで、関節のジャリジャリとした音が気にならなくなったり、運動後に「むくみが軽くなって脚がすっきりした」と感じる人もいるようです。
さらに、続けるうちに姿勢が整ったり、肩こりの軽減につながったと報告する人もいます。
大切なのは、無理をせず体の声に耳を傾けながら続けることです。
足の筋トレ・ダイエット効果を高める工夫と習慣化のコツ
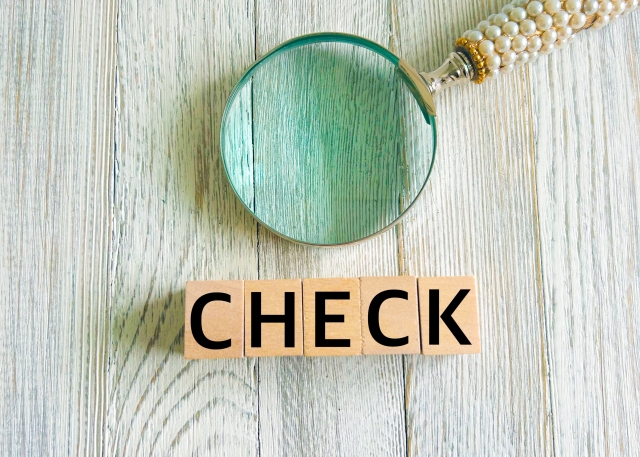
踏み台昇降は有酸素運動として脂肪燃焼や筋力アップに効果的です。
さらに効果を高めたい方や習慣化したい方に向けて、以下の工夫をおすすめします。
単なる運動としてだけでなく、生活リズムに組み込みやすくすることで長期的な成果につながります。
インターバル形式を取り入れる
例えば「ゆっくりステップ20秒→早めにステップ20秒→ゆっくり20秒」のようにリズムを変えることで心拍数が上がり、消費カロリーの増加につながります。
インターバルを取り入れると同じ時間でも効率が高まり、飽きにくく続けやすいのが特徴です。
片足ステップを加える
片足ずつ上る・下りる動作を取り入れると内腿・お尻・ふくらはぎへの刺激が増え、より引き締め効果が期待できます。
ただし、膝への負荷増加に注意し、痛みが出たらすぐ中止してください。
慣れてきたら、両手に軽めのダンベルを持って動くと上半身の筋肉も同時に刺激できます。
音楽やタイマーでテンポ管理
お気に入りの音楽をBPM(テンポ)に合わせてリズムよくステップすることで、飽きずに続けやすく、時間も感じにくくなります。
テンポを変えることで有酸素と筋トレの中間のような効果が得られ、気分転換にもつながります。
スマホアプリのタイマーを利用して、10分ごとにチャイムを鳴らすのもおすすめです。
毎日コツコツの積み重ね
「1日10分を週5日」を目標に、小さな達成感を重ねていきましょう。
膝の音も慣れて気にならなくなる場合があります。
さらに、「ながら運動」としてテレビを見ながら、ラジオを聴きながら行えば、運動のハードルが下がり習慣化しやすいです。
日記やカレンダーに運動記録をつけると、視覚的に継続の証が残りモチベーションアップにもなります。
生活習慣との組み合わせ
踏み台昇降は短時間でも効果があるため、家事の合間やリモートワーク中の休憩に取り入れるのも有効です。
例えば料理中に煮込み待ちの5分を利用する、電話中にステップするなど、生活動作に組み込むと自然と運動量が増えます。
姿勢を意識して腹筋を引き締めながら行うと体幹トレーニングにもなり、腰痛予防にもつながります。
私の場合、「好きなドラマを見ながら踏み台」というルールにしたら、気づけば15分続いていて、終わった後は全身がぽかぽかとして「カロリー使った!」という満足感に包まれました。
さらに、日を追うごとに体力がついて、階段の上り下りが楽になる実感がありました。
こうした小さな成功体験の積み重ねが、長続きの秘訣です。
無理せず、けれど続く方法を見つけるのがポイントですね。
まとめ
膝からの「ジャリジャリ音」が気になる際の踏み台昇降ですが、痛みや腫れがなく日常に支障がなければ、多くの場合は心配はいりません。
音は膝関節の自然な変化によって生じることも多く、必ずしも危険のサインではない、ということです。
ただし、長く安全に続けるためには工夫が欠かせません。
運動前後のストレッチや、適切な高さの踏み台選び、足腰にやさしいクッション性の工夫を取り入れることで膝への負担を大きく減らせます。
さらに、踏み台昇降を習慣化するには、インターバル形式や好きな音楽に合わせること、または「1日10分だけ」といった小さな目標を設定することがとても有効です。
こうした工夫は単なる体力維持にとどまらず、気分転換やストレス解消にもつながり、継続のモチベーションを高めます。
もしも途中で痛みや腫れ、音の変化が強くなってきた場合は無理をせず、早めに専門医に相談することが安心につながります。
夏でもエアコンの効いた室内で気持ちよく動き続けることで、体力や代謝を少しずつ高め、健康と美しさを同時に積み重ねていきましょう。
⚠ 本記事は一般的な情報をまとめたもので、診断や治療を目的としたものではありません。
体に不安を感じた際は、必ず医師などの専門家にご相談ください。⚠