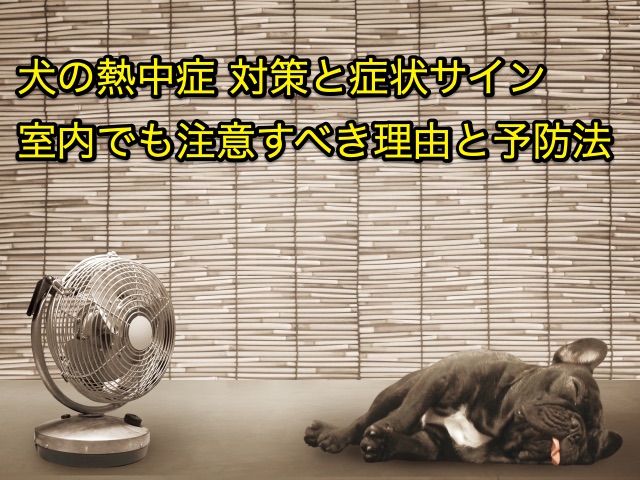夏になるとニュースで見かける「犬の熱中症」の話題。
近年では、クーラーが効いた室内にいたにもかかわらず熱中症になるケースも報告され、飼い主としては不安が募りますよね。
犬は私たち人間とは違って体温調節が苦手で、暑さからくる危険に気づきにくい動物です。
この記事では、犬の熱中症の原因や見逃しやすい症状サイン、予防の工夫、そして万が一の応急処置までを、わかりやすくご紹介します。
犬の熱中症の原因と症状とは?〜室内でも油断できない理由〜

写真はイメージです。
犬は人間のように汗をかいて体温を調整することができません。
主に「パンティング(浅く早い呼吸)」で体の熱を逃していますが、高温多湿の環境ではこの方法だけでは追いつかず、体内に熱がこもってしまうのです。
特に危険なのは以下のような環境です。
⚠️ 気温が28℃以上、湿度が70%を超える時
⚠️ 風通しの悪い部屋や車内
⚠️ 散歩後のクールダウンが不十分なとき
室内であっても直射日光が入る窓際や、エアコンの風が届かない場所、風の通らないケージ内は“熱のたまり場”になってしまうことがあります。
【主な症状サイン】
👉 はぁはぁと激しい呼吸(パンティング)
👉 よだれが多い、口の中が赤い
👉 元気がなくなる、ぼーっとする
👉 嘔吐、下痢
👉 けいれんや意識低下
特に短頭種(フレンチブルドッグ、パグなど)や老犬、子犬はリスクが高いため、こまめなチェックが大切です。
犬の熱中症を防ぐための対策と工夫〜室内での予防がカギ〜

写真はイメージです。
愛犬を守るには「暑さを避けること」「水分をこまめにとらせること」「室温と湿度を管理すること」の3つが重要です。
【室内でのポイント】
👉 エアコンは26〜28℃を目安に、湿度は50%以下をキープ
👉 サーキュレーターで空気を循環させ、ケージ内にも涼風が届くように
👉 保冷マットや冷感ベッドを活用(かじって誤飲しないタイプを選ぶ)
【🥤飲み物に注意】
水はいつでも飲めるように数か所に設置しましょう。
特に夏場は飲み水がぬるくなりがちなので、こまめに新しい冷たい水に替えるのがおすすめです。
特に老犬は体の水分保持力が低下しており、のどの渇きを感じにくかったり、水を飲みたがらなかったりすることがあります。
中には飲もうとしてもむせてしまう子も。
こうした場合は、飲みやすい高さの器を使ったり、ぬるめのスープや水分量の多いフードで補う工夫が大切です。
水分摂取量が少ない日は、排尿の様子などもこまめにチェックしてあげましょう。
【☀️ 散歩は涼しい時間帯を選んで】
早朝や日没後など、気温が下がる時間帯が愛犬とのお散歩に適しています。
SNSでは、まだ夜が明ける前の涼しい時間に歩いている飼い主さんも多く見かけます。
一方で、日中の暑さの中で散歩している姿を見ると、少し心配な気持ちになることも…。
お散歩前に地面に手を当てて熱さをチェックするのが大切です。
アスファルトは想像以上に高温になり、犬の肉球が火傷してしまうこともあります。
実際に、夏になると肉球をやけどしたワンちゃんが病院に運ばれるケースが増えると獣医師の方も話していました。
もしもの時の応急処置と動物病院へ行く判断基準

写真はイメージです。
「もしかして熱中症かも?」と感じたら、すぐに以下の応急処置をしてください。
🌡️ 【応急処置のステップ】
💨 1. 涼しい場所に移動
まずは風通しの良い日陰や、エアコンの効いた室内へ避難させましょう。
🧊 2. タオルで体を冷やす
濡らしたタオルを首・脇・内ももにあてて体温を下げてあげてください。
❄️ 3. 保冷剤や氷を活用
直接肌に触れないよう、タオルで包んだ保冷剤**を首元にあてると効果的です。
🥤 4. 水分補給は少しずつ
自力で飲めるなら一口ずつゆっくり与えましょう。無理に飲ませるのはNGです。
🚨 こんな症状があればすぐ病院へ!
👉 呼吸が荒い
👉ぐったりしている
👉身体の震えが止まらない
👉嘔吐がある
💡これらの症状があれば一刻も早く動物病院に連絡・受診してください。
🧠 後遺症にも注意
熱中症は一度回復しても、腎臓や脳にダメージが残ることがあります。
見た目で落ち着いていても、必ず獣医師の診断を受けましょう。
まとめ 日頃の工夫と観察で、愛犬の命を守る夏に
犬の熱中症は「まさかうちの子が…」という環境でも起こる可能性があります。
特に室内飼育の子ほど、エアコンがあるからと油断しがち。
日頃から「暑さへの対策」と「いつもと違う様子に気づく観察力」を大切にし、少しでも異変を感じたら早めの行動を心がけてください。
夏を乗り越えるためには、愛犬の命を守る「予防こそ最大のケア」です。
ぜひ、今日からできることを始めていきましょう。